今回は長編みで作る円の編み方のご紹介です。
法則さえわかっていれば、編み図がなくても大丈夫!
サクサク編めます。

基本的には、細編みも長編みも中長編みも
同じ法則で編んでいきます
編み図
編み図のみ見たい方のために、掲載しておきます。
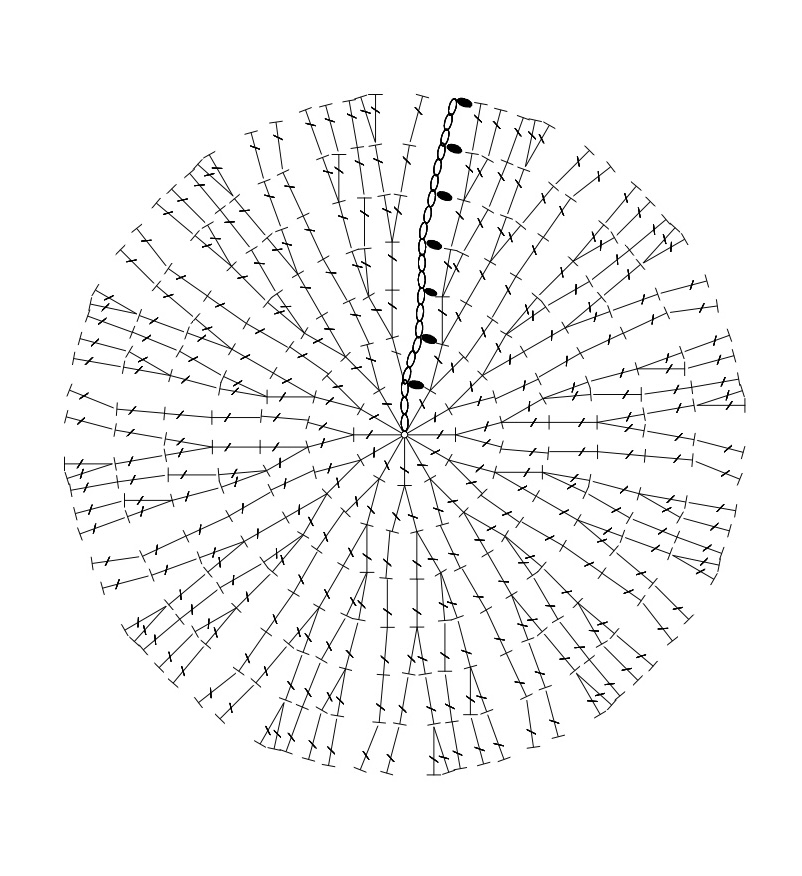
長編み円 編み方レシピ
V:長編みを1目に2回(増し目)
全ての段の始まりは、くさり編み3目スタートです。
編み終わりは、最初のくさり編みの3目目に引き抜き編みします。
尚、箇条書きの数字は段数とします・

まずは、基本的な輪の作り目からスタートします
1.輪の作り目にくさり編み3目+長編み11回
2.くさり編み3目同じ目に長編み1回、V×11(1目に長編み2回ずつの増し目が11回)
3.くさり編み3目+V、(長編み1回+V)×11回
4.くさり編み3目+長編み1回+V、(長編み+長編み+V ) ×11
5.くさり編み3目+V+長編み+長編み+長編み、(V+長編み+長編み+長編み)×11、長編み+長編み
6.くさり編み3目+長編み+長編み+長編み+V、(長編み+長編み+長編み+長編み+V )×11
7.くさり編み3目+長編み+V+長編みが5回、(V+長編みが5回)×11、長編み+長編み
8.くさり編み3目+長編み5回+V、(長編み6回+V)×11
9.くさり編み3目+長編み+V、(長編み7回+V)×11、長編み5回
10.くさり編み3目+長編み7回+V、(長編み8回+V)×11

以下段が増えるごとに
増し目の手前の長編みの回数が増えていくよ
円の編み方の法則
法則1
輪の作り目の後、1段目の数(12目)が基本となり
常に1段で12回増し目をすることになります。
法則2
編んでいて迷うところは、

今は、何目長編み編むんだっけ?
と、言うとこではないでしょうか?
少なくとも私はそうです😅
ですが、この悩みは簡単に解決されます。
長編みの目数=段数−2
例えば、6段目を編んでいるとすると
6段目−2=4
なので、長編みの数は4つとなります。

この簡単な式を覚えていれば、段数を数えれば、長編みの編む数がわかるね!
法則3
5段目以降の奇数段は増し目をずらす
5段目
長編み1回+V (増し目)、長編み3回+V (増し目)、長編み2回
最初の「長編み1回+V」と最後の「長編み2回」で合わせて『長編み3回』になるので
(長編み3回+V)×12回で法則1の『1段で12回増し目』を、きちんと守れてますね。
奇数段で増し目をずらさず、編み続けると

画像は、細編みで編んだものになりますが、
この様に角が立ってきます。
自然な円にするために、奇数段で編み目をずらすようにして下さい

細編みの円
細編みの円の始まりは、
細編み6目、8目からスタートするのが一般的ですね。
その場合、1段ごとに増やしていく増し目の数は
『法則1』に従って、
6目:1段ごとの増し目は6回
8目:1段ごとの増し目は8回
この様になります。
あとは、長編みの編み方レシピと同じになります。
こちらの記事に詳しく説明しています中長編みの円
目の数などは長編みの円と同じになります。
一つ違う所は、中長編みは立ち上がり鎖2目を1と数える場合と
1と数えない場合があります。
1と数える場合は、一周してきた時の引き抜くところが
立ち上がりの鎖2目の2目めになります。
数えない場合は、立ち上がり鎖2目を飛ばし、
最初の中長編みの頭に引き抜きます。
それ以外の編み方は、長編みと同じです。
まとめ
バックやかご、帽子などを編む時に使用する
円の編み方について説明してきました。
YouTubeの動画でもわかりやすく説明していますので
参考にしてみて下さい。
円の法則、皆様の編み物ライフのお役に立つことができれば、幸いです。
円の編み方を使った作品をご紹介


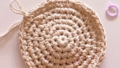







コメント